※この記事はAnswerThisによる提供でお送りしています。記事内のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。
前回医療者向けにAnswerThisの記事を作成しましたが、こちらの好評を受けて、AnswerThisから正式にご依頼を頂く形で記事を書くこととなりました。
そこで今回の記事では調べた文献をどう抽出、整理していくのか、Literature Review機能に焦点を当てていきたいと思います。
AnswerThisって何?という方はこちらをどうぞ。
AnswerThis公式サイトへのリンクはこちら

また、今回当ブログの読者用に1か月の無料トライアルと10%オフのクーポンコードを用意いただいています。ぜひ試してみてください。
クーポンコードは 「MEDICAL10」 です。
AnswerThisのTable view機能
検索して引用論文付きの回答が得られるのですが、ここからどの文献を深掘りしようかな、という時に使えるのがTable view機能です。
ボタンを押すとまずこのような形で、文献を表形式で確認できます。

ここでさらに右側にあるボタンからカラムを追加することで、文献からどのような情報を抽出するのかを自由に選択できます。
意外とこの抽出については自由度が高く、「日本語」と入れてあげるだけで、日本語での情報抽出も行ってくれます。

こうすることで次に読んでいきたい文献をさっと選びやすくなりますね。
既存のカラム以外にも使うのをお勧めしたいのは"Study design"や"Article type"と言った分類です。このまま入れると基本的に長い文章が抽出されてしまうので"Study design within 3 words"など出力数の調整をかけるような単語を入れるのが個人的にはおススメです。

▲簡潔に研究の手法を提示してくれます
これらを行うことで、質問の回答からさらに自分が読むべき文献はどれなのか?ということを上手く絞り込めると思います。一つずつアブストラクトを読んでいくよりもずっと楽ですね。
Library機能との連携
続いては選んだ文献をどう整理していくかを見ていきます。
抽出できた情報を使って読みたい文献を選び、チェックを入れた後は、それをLibraryという自分専用の論文フォルダのようなところに入れます。

▲矢印の部分から保存できます
フォルダの管理方法については論文や発表のプロジェクトごとにするのがオススメです。この辺りの整理の仕方については過去の記事で書いています。
▼タグ中心の話ですが、フォルダについても触れています
このLibrary内でもさらにTable viewを使うことができるので集めた文献を改めて整理したい、内容把握したいときに役立ちます。
また、Libraryは画面情報のボタンからZoteroやMendeleyと連携が可能です。当ブログでは無料かつ高機能な論文管理ソフトとしてZoteroを激推ししています。知らない方は是非チェックしてみてください。
Zoteroからのインポートやエクスポートができますので、別ルートで入手した論文と掛け合わせてTable Viewが作成でき、網羅的な情報抽出が可能となります。
また、実はさらにこのLibraryをSourceとして回答生成させることもできるので、表形式とQ&Aの回答と両面で利用することができます。こういった使いまわしはAll-in-oneツールならではだと思います。

また、画面上方にLibkeyという表示(青矢印)がありますが、これは施設ごとに契約している有料ジャーナルをアクセスできるようにする仕組みのようです。現在はβ版とのことですが、この有料の壁(Paywall)を突破できるかどうかは論文検索ツールの使用データベースの違いにおいて重要であると思っています。
以前ブログで紹介したOpenEvidenceはこのPaywallを突破して良質なReview記事にデータを絞り込むことでRAGとしてとても優秀な性能を示していました。データベースの違いというのが差別化の要因として大きいと感じています。
もし今後paywallを超えた先にある文献を利用できるようになるのであれば期待大ですね。
実際のワークフロー
以前の記事でObsidian-Zotero-Google NotebookLMによるワークフローを紹介しました。
今回のようなAI論文検索・管理ツールはちょうどこの間に入るような形になるのかなと思います。

文献検索をしてZoteroに取り込みつつ、Google NotebookLMほどではありませんが、簡易的に文献の内容抽出や整理を行うことができる、というのが利点だと思います。
また臨床医として論文の情報だけ利用する(必ずしも常に研究のために読むわけではない)人にとってはこうしたAI論文検索・管理ツールのほうが簡易的で良いかもしれません。
まとめ
AnswerThisでの論文管理・情報抽出方法についてまとめました。
Table viewとカラムによる情報抽出によって集めた文献から必要な情報を端的に読み取ることで、より必要な文献に集中して読み込んだり、比較が容易にできるようになります。
ぜひ皆さんも一度試してみてください。
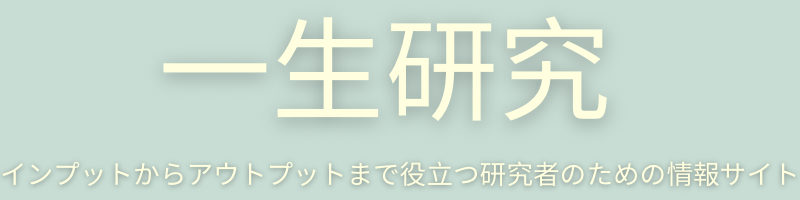


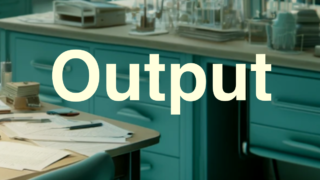

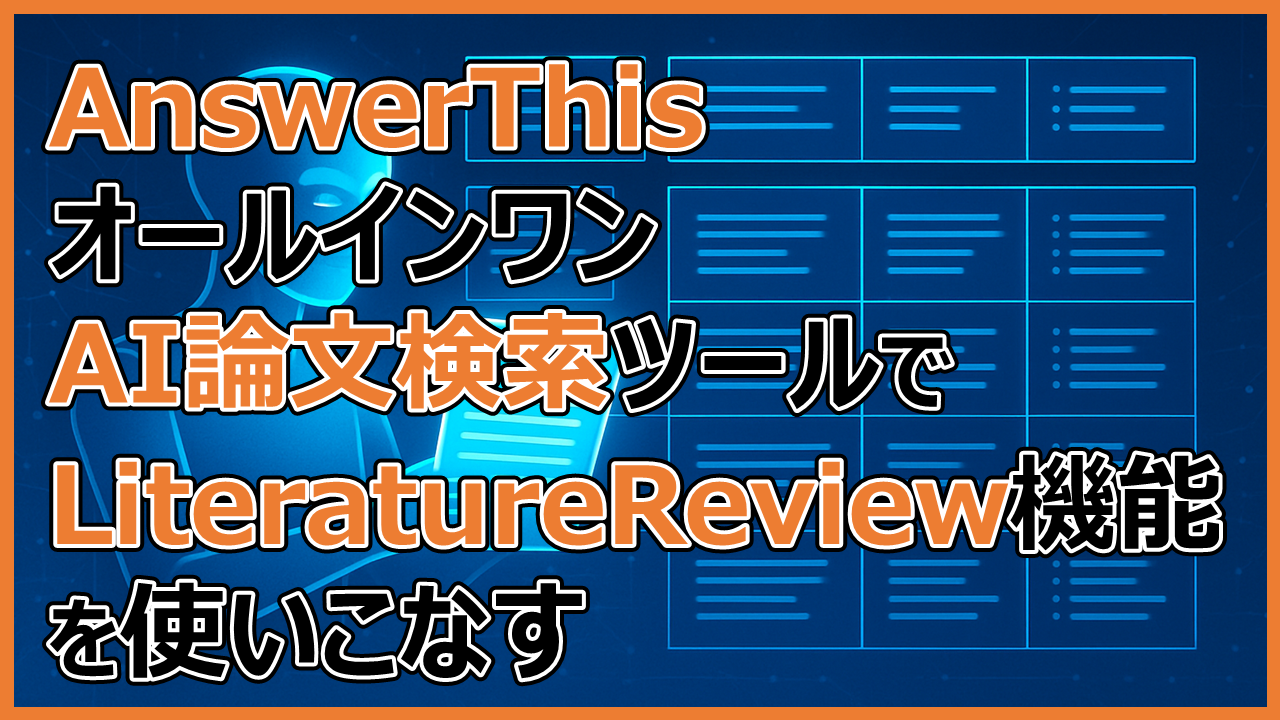
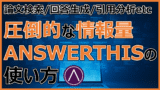
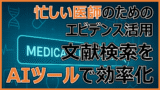
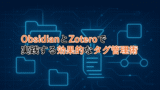

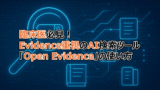
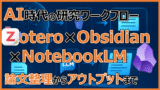
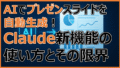
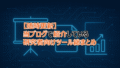
コメント